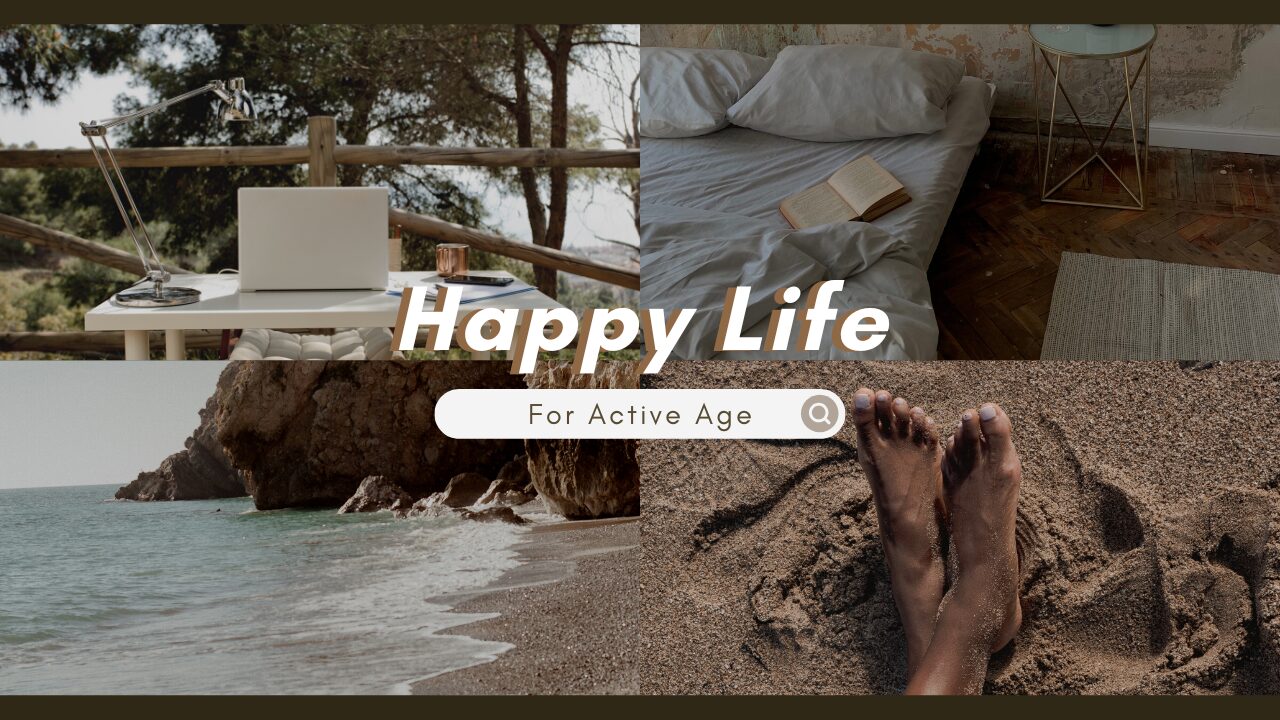
こんにちは。ライフプラン・コンサルタントの佐藤です。これまで多くのアクティブ世代の皆様から、お金や暮らしに関するご相談をいただいてまいりました。「これからの人生、子どもたちに迷惑はかけたくないな」「うちには大した財産はないけれど、相続の準備って必要なのかしら…」そんなふうに、漠然とした不安を感じながらも、何から手をつけて良いか分からず、つい後回しにしてしまっている、というお話をよく伺います。特に「相続」という言葉は、少し重たく感じてしまいますよね。でも、ご安心ください。これは、ご自身が築き上げてきた大切な資産と、何よりも「家族への想い」を、円満な形で未来へつなぐための、とても前向きな準備なのです。この記事では、2025年に向けて知っておきたい最新のルールも交えながら、皆様が具体的な第一歩を踏み出すお手伝いができればと思っています。一緒に、心穏やかな未来を描く準備を始めましょう。
円滑な資産承継とは? - 私たちの人生にどう関係するの?
「資産承継」と聞くと、なんだか難しそうに感じますよね。でも、これは決して特別なことではありません。簡単に言えば、「ご自身が大切に育んできた財産や想いを、愛するご家族へスムーズに引き継ぐための準備」のことです。現金や預貯金、ご自宅などの不動産はもちろん、最近ではインターネット銀行の口座やSNSアカウントといった「デジタル遺産」も含まれます。
では、なぜこの準備が大切なのでしょうか。それは、ご家族間の無用なトラブル、いわゆる「争族」を避けるためです。国税庁の統計によれば、相続で揉めてしまうケースの約3割は、遺産総額1,000万円以下のご家庭で起きているというデータもあります。「うちは財産が多くないから大丈夫」とは、決して言い切れないのが現実なのです。
事前の準備は、残されたご家族の負担を減らすだけでなく、ご自身の「こうしてほしい」という意思を明確に伝え、感謝の気持ちを形にする絶好の機会でもあります。資産承継は、お金の問題だけではなく、家族の絆を未来へつなぐための大切なコミュニケーションなのです。
なぜ今考えるべき? - 知っておきたい3つの理由
「まだ元気だし、考えるのは少し早いかな」と思われるかもしれません。しかし、輝く世代の皆様にこそ、「今」考えていただきたい理由が3つあります。
1. 2024年から始まった「新ルール」の影響
すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、2024年1月1日から、相続税や贈与税のルールが大きく変わりました。特に注目したいのが、生前贈与に関する変更点です。これまで、亡くなる前3年以内に行われた贈与は相続財産に加算されていましたが、この期間が段階的に7年に延長されます。つまり、より早くから計画的に贈与を進めないと、せっかくの対策が活かせなくなる可能性があるのです。一方で、「相続時精算課税制度」という仕組みの中に、年間110万円の新しい基礎控除が設けられました。この枠を使えば、将来の相続税の心配をせずに贈与ができるようになります。こうした制度変更を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて活用することが、賢い資産承継の鍵となります。
2. 人生100年時代、元気なうちに意思決定を
これからの人生は、私たちが思っている以上に長く、豊かになる可能性があります。だからこそ、心身ともに健康で、判断力がしっかりしているうちに、ご自身の意思を明確にしておくことが何よりも大切です。万が一、将来的に認知症などでご自身の意思を伝えられなくなってしまった場合、ご家族が口座の解約や不動産の売却で大変な苦労をされるケースも少なくありません。元気な今だからこそ、家族とゆっくり話し合い、遺言書の作成や任意後見制度の利用などを検討する余裕が生まれます。
3. 多様化する家族の形と資産
現代は、家族の形も資産の内容も非常に多様化しています。例えば、再婚されていてそれぞれにお子様がいらっしゃる場合や、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合など、ご家庭の状況によって最適な承継の形は全く異なります。また、前述の通り、スマートフォンの中にあるデジタル遺産も無視できません。IDやパスワードが分からなければ、誰もアクセスできなくなってしまいます。ご自身の家族構成や資産状況をきちんと把握し、誰に、何を、どのように遺したいのかを整理しておくことが、これまで以上に重要になっています。
まずはここから!家族の未来図を描くための3ステップ
□ ステップ1:現状の整理(資産と想いの棚卸し)
まずは、ご自身の資産(預貯金、不動産、有価証券、保険、デジタル資産など)と、ご家族の状況(家族構成、連絡先など)を一覧に書き出してみましょう。市販のエンディングノートを活用するのも良い方法です。そして一番大切なのは、「誰に、何を、どのように遺したいか」というご自身の想いを整理することです。
□ ステップ2:家族との対話(「想い」を伝える時間)
準備が整ったら、ご家族と話す機会を持ちましょう。「大切な話がある」と構えるのではなく、「これからのことを少し考えていてね」と、誕生日や家族が集まるタイミングで、さりげなく切り出すのがおすすめです。一方的に決めるのではなく、ご家族の意見にも耳を傾け、一緒に未来を考える姿勢が大切です。
□ ステップ3:専門家への相談予約
家族だけでは解決が難しいことや、税金の計算など専門的な知識が必要な場合は、専門家の力を借りましょう。いきなり敷居が高いと感じるなら、お住まいの自治体や金融機関が開催する無料相談会などを利用してみるのも良いでしょう。客観的なアドバイスをもらうことで、安心して準備を進められます。
専門家はどこにいる? - 頼れる相談窓口と選び方
いざ相談しようと思っても、誰に頼れば良いのか迷いますよね。それぞれに得意分野がありますので、目的に合わせて相談先を選ぶのがポイントです。
- 税理士:相続税の計算や申告、節税対策のプロフェッショナルです。「相続税がどれくらいかかるか心配」という方は、まず税理士に相談すると良いでしょう。
- 弁護士:法的な観点から、遺産分割で揉めないためのアドバイスや、法的に有効な遺言書の作成をサポートしてくれます。ご家族の関係が少し複雑な場合に心強い味方です。
- 司法書士:ご自宅など不動産の名義変更(相続登記)の専門家です。2024年4月から相続登記が義務化されたため、不動産をお持ちの方は相談が必要になります。
- ファイナンシャル・プランナー(FP):私たちのようなFPは、特定の分野だけでなく、資産全体を見渡して、皆様のライフプランに寄り添った総合的なアドバイスを行うのが得意です。「まず何から始めたらいいか分からない」という場合に、最初に相談する相手として適しています。
相談先を選ぶ際は、ご自身の話を親身に聞いてくれるか、説明が分かりやすいか、費用体系が明確か、といった点を確認し、信頼できるパートナーを見つけてくださいね。
まとめ:心豊かな未来を描くための第一歩
今回は、円満な資産承継のために今からできる準備についてお話ししました。大切なポイントを振り返ってみましょう。
- 資産承継は、財産だけでなく「家族への想い」を伝える大切な準備です。
- 2024年からの新ルールにより、より計画的で早めの対策が重要になりました。
- 元気なうちに、ご自身の意思を整理し、家族と対話する時間を持つことが「争族」を防ぐ最大の秘訣です。
- 一人で抱え込まず、必要に応じて専門家の力を借りましょう。
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。もしかしたら、少し頭が疲れてしまったかもしれませんね。でも、難しく考える必要はありません。今日できる小さな一歩は、例えば「帰りに本屋さんでエンディングノートを眺めてみる」ことかもしれませんし、「次の週末に、家族とお茶でもしながら『うちはどうしようか』と、ほんの少しだけ未来の話をしてみる」ことかもしれません。その小さな一歩が、ご自身と大切なご家族の、心豊かで穏やかな未来へとつながっていきます。私たちは、いつでも皆様の輝く人生を応援しています。
免責事項
本記事で提供される情報は、記事作成時点のものです。税制、年金、法律などの制度は将来変更される可能性がありますので、必ず公式サイトや専門家にご確認ください。
また、本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品、法律、税務上のアドバイスを行うものではありません。個別の状況に応じた最終的な決定は、税理士、弁護士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家にご相談の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。







