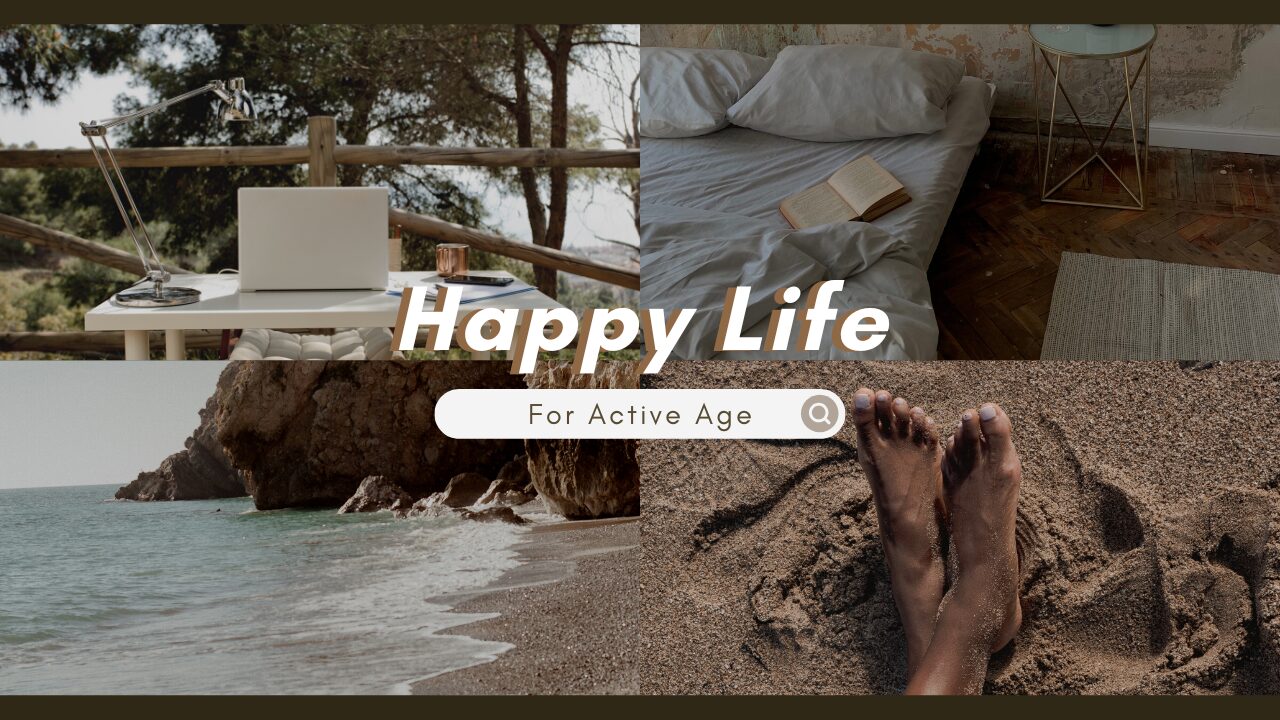
こんにちは。ライフプラン・コンサルタントの佐藤です。人生の円熟期を迎え、これからの時間をどう豊かに過ごそうかと心を弾ませている皆様。趣味や旅行の計画を立てる一方で、「そろそろ、財産のことや家族の将来についても考えておかないと…」と、心の片隅で少し気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「相続」と聞くと、なんだか難しくて縁遠い話、あるいは少しネガティブなイメージをお持ちかもしれません。でも、私はこれを「大切なご家族へ、ご自身の想いを繋ぐための最後のラブレター」だと考えています。ご自身が築き上げてきた大切な資産と、それ以上に大切なご家族への愛情を、きちんと形にして残すための準備なのです。特に、2025年に向けて制度が新しくなり、今、このタイミングで考え始めることがとても重要になりました。この記事では、専門用語をできるだけ使わず、皆様が安心して第一歩を踏み出せるよう、心を込めてご案内いたします。
遺産分割と生前贈与とは? - 私たちの人生にどう関係するの?
まず、言葉のイメージを少しだけほぐしてみましょう。「遺産分割」とは、万が一のことがあった後、ご家族が財産をどう分けるかのお話し合いのことです。そして「生前贈与」とは、ご自身が元気なうちに、ご自身の意思で、大切な方に財産を贈ることを指します。
なぜ、この二つが私たちの人生にとって大切なのでしょうか。それは、残されたご家族が財産の分け方をめぐって心を悩ませたり、関係がぎくしゃくしてしまったりする「争族」という悲しい事態を避けるためです。財産の多少にかかわらず、こうしたトラブルはどのご家庭にも起こり得ます。あらかじめご自身の考えをまとめ、意思を伝えておくことで、ご家族は安心して手続きを進めることができます。それは、財産そのもの以上に価値のある、「安心」という贈り物になるのです。また、生前贈与は、「ありがとう」の気持ちを直接伝えながら資産を渡せる、とても心温まる方法でもあります。お孫さんの教育資金や、お子様の住宅購入の援助など、ご家族の夢を応援する形で、ご自身の資産が活かされるのを見届けることができるのも、大きな喜びと言えるでしょう。
なぜ今考えるべき? - 知っておきたい3つの理由
「まだ元気だし、もう少し先でいいかな」と思われるかもしれません。しかし、輝く世代の皆様にこそ、「今」考えていただきたい理由が3つあります。
理由1:2024年から始まった「新しいルール」
最も大きな理由が、制度の変更です。これまでは、亡くなる前3年以内の生前贈与は相続財産に加算されていましたが、2024年1月1日以降の贈与からは、この期間が段階的に延長され、最終的に亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に加算されることになりました。これはつまり、より早い時期から計画的に贈与を進めることが、以前にも増して重要になったということです。「いつか」ではなく「今」から準備を始めることで、より多くの選択肢を持つことができます。
理由2:何より大切な「家族の絆」を守るため
遺されたご家族にとって、遺産分割の話し合いは精神的にも大きな負担となります。そこに明確な指針がないと、ささいな意見の食い違いから、深い溝が生まれてしまうことも少なくありません。ご自身が元気なうちに、なぜそのように財産を分けたいのか、その背景にある「想い」を伝えておくこと。遺言書やエンディングノートといった形で「想い」を明確に伝えることは、残されたご家族がお互いを思いやり、円満に話し合いを進めるための、何よりの道しるべとなります。
理由3:ご自身の豊かな人生プランのため
相続の準備は、ご自身のこれからの人生を見つめ直し、より豊かにするための絶好の機会でもあります。ご自身の資産を整理する中で、「これは子どもたちに」「これは社会のために」「そして、これは自分たちの趣味や旅行のために」と、お金の使い道を改めて考えることができます。資産を棚卸しすることで、これからの人生で本当にやりたいこと、楽しみたいことへの資金計画が明確になり、よりアクティブで充実した日々を送るための準備にも繋がるのです。
まずはここから!家族円満のための相続準備リスト
□ ステップ1:ご自身の資産を書き出してみる
まずは、どんな財産がどれくらいあるのかを把握することから始めましょう。預貯金、不動産、株式、保険など、簡単なメモで構いません。一覧にしてみることで、全体像が見えてきます。
□ ステップ2:「想い」を言葉にしてみる
誰に、何を、どのように残したいですか? なぜそう思うのか、その理由も一緒に書き留めてみましょう。市販のエンディングノートなどを活用するのも良い方法です。これは法的な効力はありませんが、ご自身の気持ちを整理し、ご家族に伝えるための大切な資料になります。
□ ステップ3:ご家族と話すきっかけを作る
一度に全てを話そうとせず、まずはご自身の想いを伝えてみることから始めましょう。「最近、これからのことを考えていてね…」と、穏やかな雰囲気で切り出すのがポイントです。ご家族の考えを聞く良い機会にもなります。
□ ステップ4:専門家への相談を検討する
具体的な進め方に迷ったら、専門家の力を借りるのが一番の近道です。次の章で、どんな専門家がいるのかをご紹介しますね。
専門家はどこにいる? - 頼れる相談窓口と選び方
いざ準備を始めようと思っても、一人で全てを抱える必要はありません。それぞれの分野のプロフェッショナルが、皆様の心強い味方になってくれます。
- 税理士:相続税や贈与税の計算、節税対策など、税金に関する相談のプロです。「うちの場合は税金がかかるの?」といった疑問に明確に答えてくれます。
- 弁護士:法的な効力を持つ遺言書の作成や、ご家族間の意見調整など、法律の面からサポートしてくれます。複雑な事情がある場合に頼りになります。
- 司法書士:ご自宅など不動産の名義変更(相続登記)の専門家です。相続登記は2024年4月から義務化されており、重要な手続きです。
- ファイナンシャル・プランナー(FP):お金に関する幅広い視点から、相続だけでなく、これからの生活費や趣味の資金計画まで含めた総合的なアドバイスをしてくれます。
相談先を選ぶ際は、相続に関する実績が豊富で、何よりも皆様のお話に親身に耳を傾けてくれる人柄かどうかを大切にしてください。自治体や金融機関などで開催される無料相談会などを利用して、まずは気軽に話を聞いてみるのも良いでしょう。
まとめ:心豊かな未来を描くための第一歩
ここまで、お疲れさまでした。相続や贈与について考えることは、決して難しいことばかりではありません。むしろ、ご自身の人生を振り返り、大切なご家族への感謝を形にする、とても前向きな活動です。
- 相続準備は、ご家族への「想い」を伝える大切な贈り物です。
- 2024年から生前贈与のルールが変わり、早めの準備がより重要になりました。
- まずは「資産の書き出し」と「ご自身の想いをまとめる」ことから始めてみましょう。
- 一人で悩まず、必要に応じて専門家の力を借りることを恐れないでください。
さあ、今日からできる小さな一歩を踏み出してみませんか。例えば今夜、お茶でも飲みながら、ご自身の資産やご家族への想いを、ノートの1ページに書き出してみる。その小さな行動が、あなたとあなたの大切なご家族の、心豊かで穏やかな未来を描くための、確かな第一歩となるはずです。私たちがいつでも、そのお手伝いをさせていただきます。
免責事項
本記事で提供される情報は、記事作成時点のものです。税制、年金、法律などの制度は将来変更される可能性がありますので、必ず公式サイトや専門家にご確認ください。
また、本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品、法律、税務上のアドバイスを行うものではありません。個別の状況に応じた最終的な決定は、税理士、弁護士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家にご相談の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。






