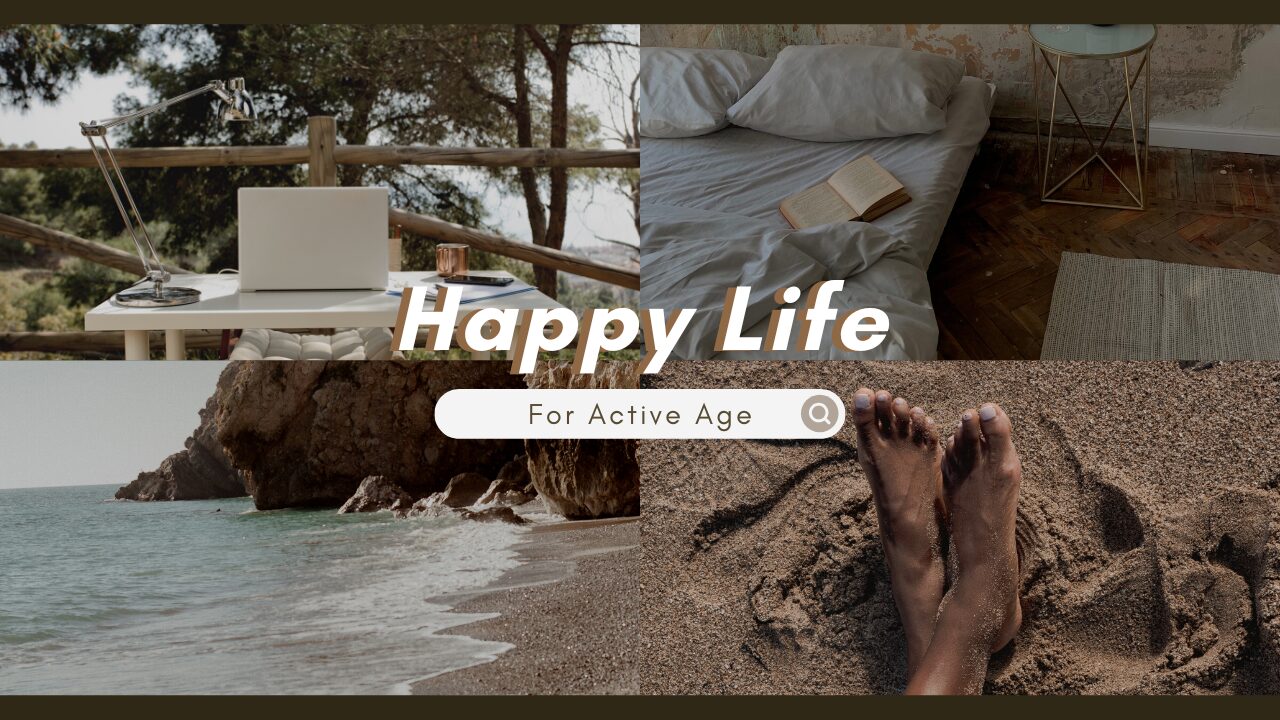
これまでの人生で大切に育み、築き上げてこられた資産や、ご家族へのあたたかい想い。「そろそろ、次の世代へどう繋いでいくかを考えないと…」と、心のどこかで感じていらっしゃるかもしれませんね。一方で、「相続の話なんて、何から手をつけていいか分からない」「家族と話し合うのは、なんだか気が引ける」と感じる方も少なくないのではないでしょうか。
テレビドラマで見るような「争族」は、決して他人事ではありません。しかし、ほんの少し早く準備を始めるだけで、ご自身の想いをしっかりと形にし、大切なご家族がこれからも円満に過ごせる未来を描くことができるのです。この記事では、経験豊富なライフプラン・コンサルタントとして、皆様のそんなお気持ちに寄り添いながら、2025年からの新しいルールも踏まえた「家族円満のための資産承継」について、具体的な第一歩を分かりやすくご案内いたします。どうぞ、肩の力を抜いて、一緒に未来への準備を始めてみましょう。
「想いを繋ぐ準備」とは? - 私たちの人生にどう関係するの?
「相続対策」と聞くと、なんだか難しい手続きや税金の話ばかりを想像してしまいがちですが、その本質はもっと温かいものです。それは、ご自身が大切にしてきたものや感謝の気持ちを、愛するご家族へきちんと伝えるための「想いを繋ぐ準備」にほかなりません。具体的には、「遺言」と「生前贈与」という二つの方法が中心となります。
遺言は、ご自身の財産を「誰に」「何を」「どれだけ」遺したいかという最終的な意思を記した、いわば「未来のご家族への手紙」です。法的な効力を持つため、ご自身の想いを確実に実現させることができます。
生前贈与は、ご自身が元気なうちに、ご家族などへ財産を贈ることです。お子様やお孫様の住宅購入や教育資金など、必要なタイミングで支援できるだけでなく、将来の相続税の負担を軽くする効果も期待できます。何より、ご自身の目で「ありがとう」という笑顔を見られるのが、一番の喜びかもしれませんね。
これらの準備は、単なる財産の引き継ぎではありません。ご家族があなたの想いを深く理解し、感謝とともに受け取ることで、家族の絆をより一層深めるための、大切なコミュニケーションなのです。
なぜ今考えるべき? - 知っておきたい3つの理由
「まだ先のこと」と思いがちな資産承継の準備ですが、実は「今」始めるべき明確な理由があります。特に、最近の制度変更は、私たちの計画に直接影響を与えます。
- 理由1:生前贈与の新ルールがスタートしたから
これまで、亡くなる前3年以内に行われた生前贈与は、相続財産に加算されて計算されていました。しかし、2024年1月1日以降の贈与からは、この期間が段階的に「7年」へと延長されます。つまり、より早めに計画を立てて贈与を始めないと、せっかくの対策が将来の税負担軽減に繋がりにくくなる可能性があるのです。 - 理由2:新しい非課税制度が使いやすくなったから
「相続時精算課税制度」という、少し複雑な名前の制度があります。これまでは使い勝手が難しい面もありましたが、2024年から毎年110万円までの基礎控除(非課税枠)が新設されました。これにより、まとまった資金を贈与したい場合などに、新しい選択肢として活用しやすくなりました。ご自身の状況に合わせて、暦年贈与(毎年110万円まで非課税)と賢く使い分けることが大切です。 - 理由3:心と身体が元気なうちに、じっくり考えたいから
資産承継の準備は、ご自身の想いを整理し、ご家族と対話し、時には専門家の意見を聞きながら、時間をかけて進めるのが理想です。判断力や体力が十分にある輝く世代の今だからこそ、冷静かつ前向きに、ご自身とご家族にとって最善の形を考え抜くことができます。万が一の認知症などへの備えとしても、意思が明確なうちに準備を始めることは、ご家族を守ることに繋がります。
まずはここから!家族円満のための「想いを繋ぐ」3ステップ
何から始めたら良いか分からない…という方は、まずこの3つのステップから試してみてください。
□ ステップ1:ご自身の「想い」と「資産」の棚卸し
まずはノートを1冊用意して、①ご家族一人ひとりへの想いや伝えたいこと、②ご自身の資産(預貯金、不動産、有価証券など)の一覧、を書き出してみましょう。正確でなくても構いません。全体像を把握することが第一歩です。
□ ステップ2:きっかけを作って家族と話してみる
「この間のニュースで見たんだけど…」「これからのことを少し考えていてね」など、さりげない言葉で大丈夫です。まずは、ご自身が家族を大切に想っていること、そして将来のことで心配させたくないという気持ちを伝えることから始めてみましょう。深刻にならず、穏やかな雰囲気で話すのがポイントです。
□ ステップ3:専門家への相談を検討する
少しでも具体的な話になったり、疑問点が出てきたりしたら、専門家の力を借りるのが安心です。お住まいの地域の金融機関や自治体で開催される無料相談会などを探してみるのも良いでしょう。まずは情報収集のつもりで、気軽に予約してみるのがおすすめです。
専門家はどこにいる? - 頼れる相談窓口と選び方
ご家族だけで解決するのが難しい問題に直面したとき、専門家は心強い味方になってくれます。相談内容によって、頼れる専門家は異なります。
- 税理士:相続税や贈与税の計算、申告手続きなど、税金に関するプロフェッショナルです。具体的な節税対策を相談したい場合に最適です。
- 弁護士:ご家族の関係が複雑な場合や、将来的なトラブルを法的に防ぎたい場合に頼りになります。遺言書の作成においても、法的な観点から的確なアドバイスをもらえます。
- 司法書士:不動産の名義変更(相続登記)の専門家です。また、遺言書の作成支援や、遺言執行者としての役割も担ってくれます。
- ファイナンシャル・プランナー(FP):お金に関する幅広い知識を持ち、ご家庭の状況全体を俯瞰して、資産承継を含めたライフプラン全般の相談に乗ってくれます。誰に相談していいか分からない時の、最初の窓口としても適しています。
専門家を選ぶ際は、専門分野や費用だけでなく、「この人になら安心して話せる」と思える相性も大切です。初回の相談などを利用して、話しやすさや人柄を確認することをおすすめします。
まとめ:心豊かな未来を描くための第一歩
今回は、アクティブ世代の皆様が、心穏やかにこれからの人生を楽しむための「想いを繋ぐ準備」についてお話ししました。大切なポイントを振り返ってみましょう。
- 資産承継の準備は、家族への感謝を伝える「想いを繋ぐバトンタッチ」です。
- 生前贈与のルールが変わり、早めの計画がより重要になりました。
- まずはご自身の想いと資産を書き出し、家族と話すきっかけを作ることが大切です。
- 分からないことは一人で抱え込まず、信頼できる専門家を味方につけましょう。
何から始めれば…と立ち止まってしまったら、まずは「今日からできる小さな一歩」を踏み出してみませんか。例えば、大切な人への感謝の気持ちを手紙に一行だけ書いてみる。それだけでも、あなたの想いを形にする素晴らしいスタートです。この記事が、皆様の輝く未来への、はじめの一歩となれば幸いです。
免責事項
本記事で提供される情報は、記事作成時点のものです。税制、年金、法律などの制度は将来変更される可能性がありますので、必ず公式サイトや専門家にご確認ください。
また、本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品、法律、税務上のアドバイスを行うものではありません。個別の状況に応じた最終的な決定は、税理士、弁護士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家にご相談の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。








