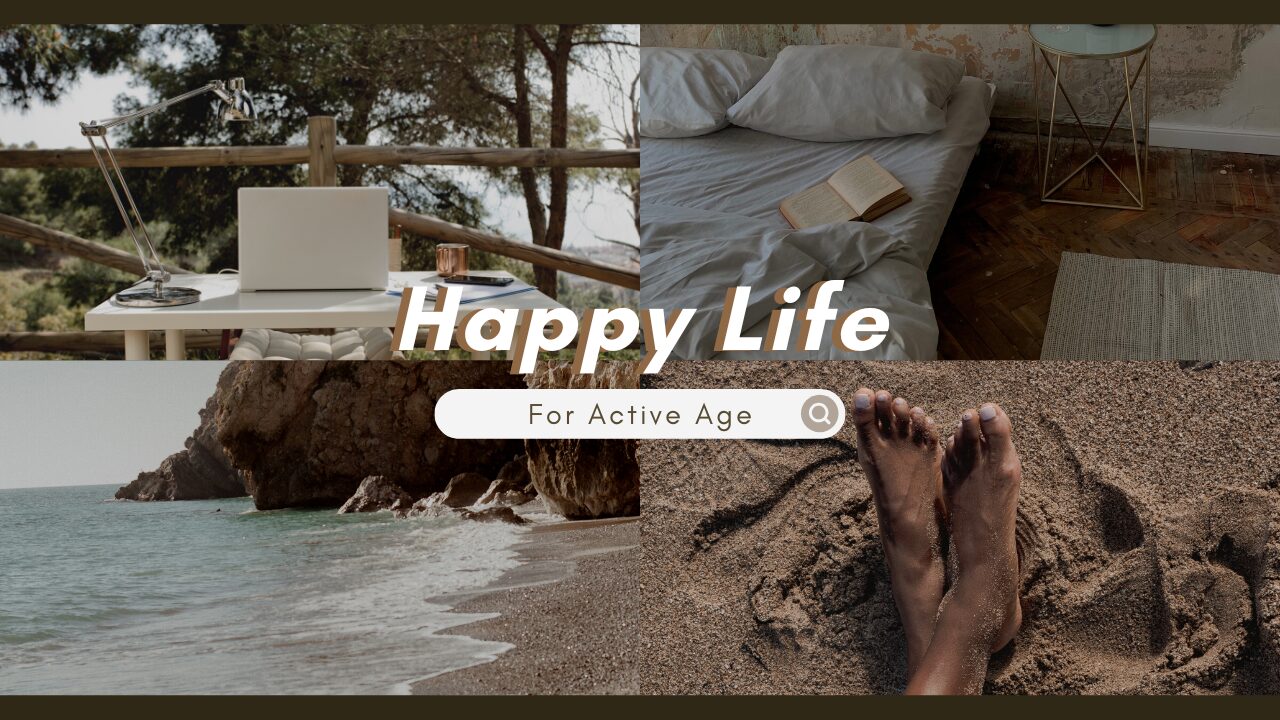
「うちには大した財産はないから関係ない」「まだ先のことだから…」そう思っていらっしゃる方も、多いのではないでしょうか。長年、多くの方のライフプラン相談に乗ってきましたが、資産承継のお話になると、少し身構えてしまうお気持ちは、とてもよく分かります。しかし、これからの人生を、そして大切なご家族の未来を心豊かに過ごすために、少しだけ耳を傾けていただけたら嬉しいです。
実は、ご家族の間で起こる「争族」と呼ばれるトラブルは、資産の多い少ないとは関係なく、ちょっとした想いのすれ違いから生まれることがほとんどなのです。そして、2025年からは、私たちの資産承継に関わるルールも新しくなります。この記事では、輝く世代の皆様が、家族の絆を未来へつなぐための「円満な資産承継」について、今からできる第一歩を、一緒に考えていきたいと思います。どうぞ、肩の力を抜いて、お茶でも飲みながら読み進めてみてくださいね。
資産承継とは?- 私たちの人生にどう関係するの?
「資産承継」と聞くと、なんだか難しそうに聞こえますよね。でも、簡単に言えば「ご自身がこれまで築き上げてこられた大切な財産と、そこに込められた『想い』を、次の世代へ円満に引き継いでいくための準備」のことです。これは、単なるお金や不動産の手続きではありません。ご家族への感謝の気持ちを形にし、これからも仲良く暮らしてほしいという願いを伝える、とても大切なコミュニケーションなのです。
では、なぜ準備ができていないと「争族」になってしまうのでしょうか。例えば、「長男だから多くもらえるはず」「介護を頑張ったのだから、その分を考慮してほしい」といった、ご家族それぞれの期待や想いが、言葉にされないままぶつかり合ってしまうからです。遺されたご家族が、お金のことで関係がぎくしゃくしてしまうのは、誰にとっても悲しいことですよね。資産の多少にかかわらず、すべての家族に関わる大切なテーマであると、心に留めておいていただきたいと思います。
なぜ今考えるべき?- 知っておきたい3つの理由
「いつか考えよう」と思っているうちに、時間はあっという間に過ぎてしまいます。今、このタイミングで考えるべき、3つの大きな理由があります。
理由1:2025年に向けて、贈与のルールが変わるから
「生前贈与」という言葉を聞いたことはありますか?元気なうちにご自身の財産を家族に贈与することですが、このルールが新しくなっています。特に知っておきたいのが、亡くなる直前の贈与は、相続財産に持ち戻されて計算される期間です。これまでは亡くなる前「3年以内」の贈与が対象でしたが、2024年1月1日以降の贈与からは、この期間が段階的に「7年」へと延長されます。つまり、より早めに計画を立てておくことが、ご自身の想いを反映させる上で有利になるのです。一方で、年間110万円まで非課税で贈与できる新しい仕組みも始まるなど、制度は複雑になっています。だからこそ、早めに情報を集め、ご自身に合った方法を検討することが大切です。
理由2:人生100年時代の「もしも」に備えるため
私たちは今、人生100年時代を生きています。これは素晴らしいことですが、一方で、年齢を重ねると思わぬ病気や判断能力の低下といったリスクと向き合う時間も長くなります。もし、認知症などでご自身の意思表示が難しくなってしまうと、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりと、ご家族が困ってしまうケースも少なくありません。ご自身の財産を「誰のために、どう使ってほしいか」という意思を、ご自身の意思が明確なうちに準備を進めることが、ご自身とご家族の安心につながります。
理由3:家族への「想い」を伝える最高の機会だから
資産承継の準備は、財産を分けるための事務的な作業ではありません。むしろ、ご自身の人生を振り返り、ご家族への感謝や未来への願いを伝えるための、最高の機会です。「この家は、みんなで笑い合った思い出がたくさん詰まっているから、大切にしてほしい」「このお金は、孫の教育のために役立ててほしい」といった想いを伝えることで、財産は単なるモノやお金ではなく、家族の絆を深める温かい贈り物になります。準備の過程でご家族と対話する時間は、何にも代えがたい貴重なものになるはずです。
ケース別・やることリスト
「何から手をつければいいのか分からない…」という方のために、簡単なステップをご用意しました。ご自身の状況に合わせて、できることから始めてみましょう。
【まだ何も始めていない方向け】
□ ステップ1:まずは自分を知ることから
難しく考えず、まずは「エンディングノート」を一冊、用意してみませんか。エンディングノートの作成は、ご自身の資産や想いを整理する第一歩です。預貯金、保険、不動産などの財産を書き出すだけでなく、「家族に伝えたいこと」のページに感謝の言葉を綴るだけでも、心が整理されますよ。
【少し考え始めている方向け】
□ ステップ2:ご家族と話す「きっかけ」を作る
いきなり「相続の話をしよう」と切り出すのは、少し勇気がいりますよね。例えば、「最近、友人が実家の片付けで大変だったみたいで…」「将来のことを、一度みんなで話しておきたいなと思って」など、ご自身の体験や想いをきっかけに、和やかな雰囲気で話し始めるのがおすすめです。大切なのは、家族と「想い」を共有する時間を持つことです。
【具体的に進めたい方向け】
□ ステップ3:専門家の知恵を借りる
ご家族との話し合いで方向性が見えてきたら、専門家に相談してみましょう。いきなり費用を心配せずとも、市町村や金融機関が開催する無料相談会などを利用するのも一つの手です。まずは情報を集めるつもりで、気軽に足を運んでみましょう。
専門家はどこにいる?- 頼れる相談窓口と選び方
いざ相談しようと思っても、誰に頼ればいいのか迷いますよね。相談内容によって、頼れる専門家は異なります。
- 税理士:相続税が心配な方、節税について具体的なアドバイスが欲しい場合に。
- 弁護士:遺言書の作成を法的に万全にしたい、ご家族の関係が少し複雑で将来揉める可能性が心配な場合に。
- 司法書士:ご自宅など不動産の名義変更(相続登記)の相談が中心になります。
- ファイナンシャル・プランナー(FP):お金の専門家として、資産全体の状況を把握し、これからのライフプラン全体を見据えた総合的なアドバイスが欲しい場合に。
- 信託銀行などの金融機関:遺言書の作成・保管・執行までを任せる「遺言信託」や、認知症対策としての「家族信託」など、幅広いサービスを提供しています。
選ぶ際のポイントは、「ご自身の話を親身に聞いてくれるか」「専門用語を使わず、分かりやすく説明してくれるか」「料金体系が明確か」の3つです。いくつかの相談窓口で話を聞いてみて、ご自身が「この人なら信頼できる」と思えるパートナーを見つけることが大切です。
まとめ:心豊かな未来を描くための第一歩
ここまで、お疲れ様でした。資産承継は、決して後ろ向きな準備ではありません。むしろ、これからの人生をより安心して、自分らしく輝かせるための、前向きな活動です。
- 資産承継は、資産の大小にかかわらず、すべての家族にとって大切な「想いを伝える」機会です。
- 2025年に向けた制度変更を考えると、早めに準備を始めることが、ご家族にとってもご自身にとってもプラスになります。
- 難しく考えず、まずはご自身の資産と想いを書き出してみることから始めましょう。
今日からできる小さな一歩は、エンディングノートを本屋さんで手に取ってみることかもしれません。あるいは、ご家族に「いつもありがとう」と、改めて伝えてみることかもしれません。その小さな一歩が、あなたとあなたの大切なご家族の、心豊かな未来へとつながっています。私たちは、いつでもあなたの輝く人生を応援しています。
免責事項
本記事で提供される情報は、記事作成時点のものです。税制、年金、法律などの制度は将来変更される可能性がありますので、必ず公式サイトや専門家にご確認ください。
また、本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品、法律、税務上のアドバイスを行うものではありません。個別の状況に応じた最終的な決定は、税理士、弁護士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家にご相談の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。







