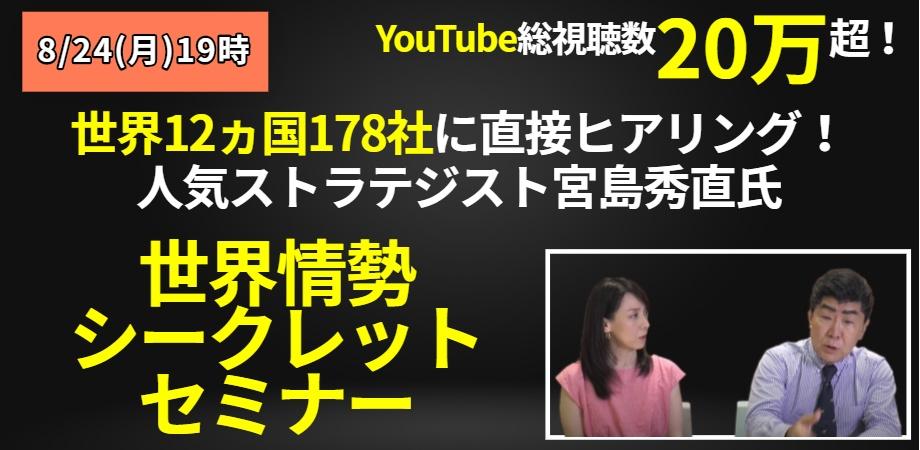マーケット概況(2025年7月2日)
2025年7月2日(水)の米国市場は、独立記念日の祝日を前にした薄商いの中、発表された経済指標を受けて主要株価指数が上昇しました。ISM非製造業景況指数が市場予想を上回り、景気の底堅さが示されたことが好感され、投資家心理が改善。ダウ工業株30種平均は前日比98ドル高で取引を終えました。ハイテク株中心のナスダック総合指数も小幅ながら続伸し、底堅さを見せました。
一方、エネルギー市場では中東情勢への警戒感が根強く、WTI原油先物価格は続伸し、一時1バレル84ドル台に乗せるなど、約2ヶ月ぶりの高値圏で推移しています。為替市場では、米国の良好な経済指標を受けてドルが買われ、ドル円は一時1ドル144円台後半まで上昇しました。金利市場では、景気のソフトランディング期待から米国10年債利回りがわずかに上昇。市場全体としては、米経済の堅調さへの安堵感と、地政学リスクや原油高への警戒感が綱引きする展開となりました。
中東情勢の緊迫化継続、原油供給への懸念燻る
イランとイスラエルの対立や、紅海でのフーシ派による商船への攻撃など、中東を巡る地政学リスクは依然として高く、原油価格を高止まりさせる主な要因となっています。7月2日には、イランが核開発プログラムを再び加速させているとの報道も一部で見られ、市場の神経を尖らせました。現時点で大規模な軍事衝突には至っていませんが、偶発的な衝突がホルムズ海峡の封鎖などに繋がれば、原油供給に深刻な影響を与えかねません。エネルギー価格の上昇は世界的なインフレ再燃のリスクをはらんでおり、各国中央銀行の金融政策にも影響を与えるため、市場は引き続き中東の動向を注視しています。
米中対立の新たな火種か?半導体分野での規制強化
米商務省が、先端半導体の製造に不可欠な「ゲートオールアラウンド(GAA)」技術に関する対中輸出規制を強化する方針であると報じられました。これは、中国の半導体技術の発展を核心部分で食い止める狙いがあり、米中間の技術覇権争いが新たな段階に入ったことを示唆しています。この規制が正式に導入されれば、対象となる米国企業だけでなく、グローバルなサプライチェーン全体に影響が及ぶ可能性があります。中国側の反発も必至で、両国の対立がさらに激化するリスクが市場の重しとなっています。
韓国、統計開始以来初の人口「自然減」に直面
韓国統計庁が発表した最新の人口動向によると、2024年の合計特殊出生率が過去最低を更新する見込みであることが改めて示されました。死亡数が出生数を上回る「人口の自然減」はすでに始まっており、このままでは100年後に人口が現在の7分の1にあたる約700万人台まで減少するとの民間予測も現実味を帯びています。深刻な労働力不足、内需の縮小、社会保障制度の持続可能性への懸念は、韓国経済が直面する構造的な課題です。政府は対策を打ち出していますが、効果は限定的で、長期的な経済成長への深刻な足かせとなるでしょう。
釜山も例外ではない、韓国の深刻な地方消滅危機
韓国第二の都市である釜山でさえ、若者世代の流出と急激な高齢化により、人口減少が深刻な問題となっています。英国のメディアもこの問題に注目し、地方都市のインフラ維持や行政サービスの低下が懸念される「地方消滅」のリスクを報じました。釜山港を中心とした物流や製造業への打撃も懸念され、不動産市場の低迷にも繋がりかねません。ソウル一極集中が進む中で地方経済が疲弊しており、韓国社会の格差拡大を象徴する問題として、国内外から注目されています。
日米貿易交渉、次回協議に向けた事務レベル調整が続く
7回目とされる公式な関税協議はまだ開催されていませんが、日米両政府は電気自動車(EV)のバッテリーに使用される重要鉱物のサプライチェーンに関する協定など、個別テーマでの実務的な協議を続けています。目下の焦点は、11月の米大統領選挙の結果が、今後の貿易政策にどう影響するかです。トランプ前大統領が返り咲いた場合、再び広範な輸入品に関税が課される可能性も指摘されており、日本企業は事業戦略の再検討を迫られています。日本政府は、現行の有利な条件を維持すべく、水面下での交渉を続けている模様です。
【免責事項】
上記の情報は、公開情報に基づいて作成されたものですが、その正確性を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。