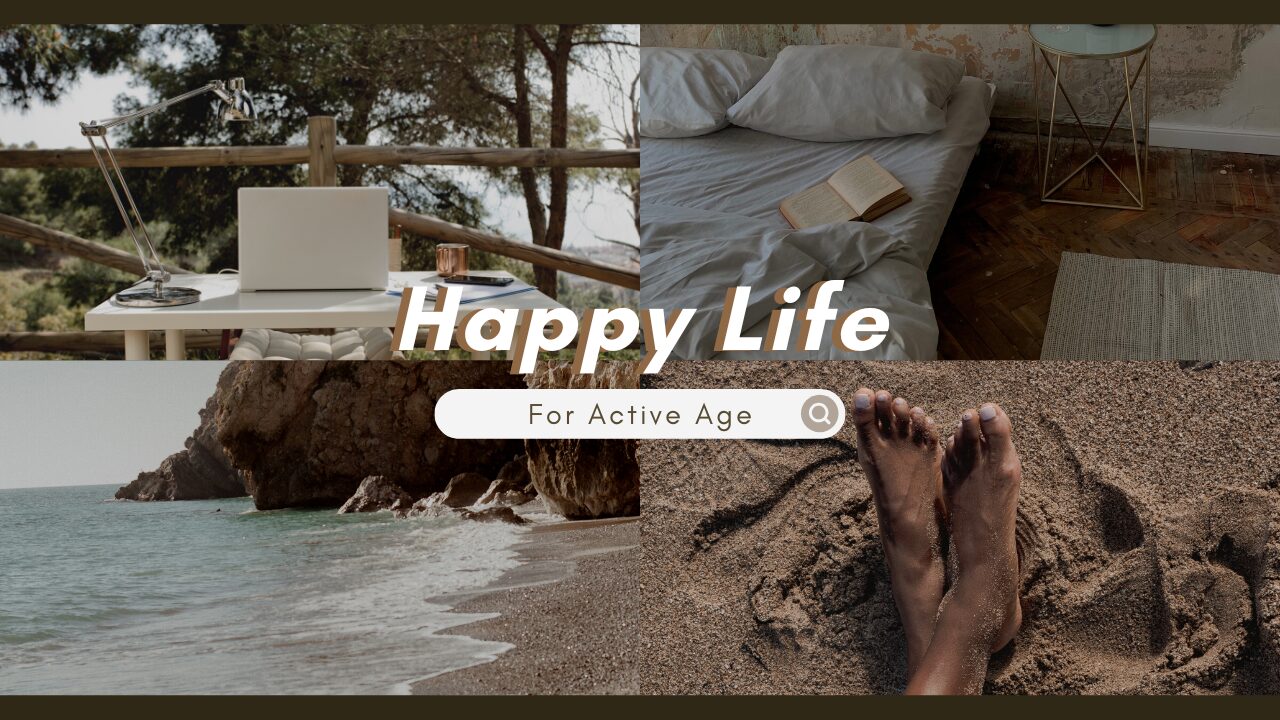
人生の豊かな実りの季節を迎えられた皆様、こんにちは。ライフプラン・コンサルタントの佐藤です。これまで一生懸命に働き、ご家族のために築いてこられた大切な資産や、言葉にはできないほどの深い想い。それを、どうやって次の世代に繋いでいこうか…と、ふとお考えになることはありませんか?
「相続なんて、まだ先の話」「うちの家族は仲が良いから大丈夫」そう思っていても、些細なことから家族の間に溝が生まれてしまうことは、決して珍しいことではありません。この記事では、そんな皆様の心にそっと寄り添い、専門用語をできるだけ使わずに、大切な資産と想いを円満に引き継ぐための具体的な方法を、2025年からの新しいルールも踏まえて丁寧にご案内します。読み終わる頃には、きっと『これなら私にもできるかも』と、未来への第一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。
「争族」と生前対策 - 私たちの人生にどう関係するの?
最近よく耳にする「争族」という言葉。まるでテレビドラマの中の話のように聞こえるかもしれませんが、実はとても身近な問題です。大切なご家族が、財産を巡って言い争う…そんな悲しい事態は、誰だって避けたいですよね。
多くの場合、「争族」の原因は財産の金額の大小ではありません。むしろ、「なぜこの分け方なの?」「何も聞かされていなかった」といった、コミュニケーション不足からくる不公平感や寂しさが引き金になることが多いのです。つまり、円満な資産承継の鍵は、金額だけでなく「想い」をきちんと伝えることにあります。
そこで大切になるのが、「遺言」や「生前贈与」といった事前の準備です。これらは単なる財産分けの道具ではありません。ご自身の人生を振り返り、「ありがとう」の気持ちや「こう生きてほしい」という願いを込めた、ご家族への最後の手紙のような役割を果たしてくれるのです。あなたの想いが伝われば、残されたご家族も納得し、互いを思いやりながら、あなたの意志を大切に受け継いでくれることでしょう。
なぜ今考えるべき? - 知っておきたい3つの理由
「まだ元気だし、もう少し先でいいかな」と思われるかもしれません。しかし、準備を始めるなら「今」が最適な理由が3つあります。
理由1:2025年から本格化する「新しいルール」
これまで、亡くなる前3年以内に行われた贈与は、相続財産に含めて相続税を計算するというルールがありました。ところが、制度が変わり、2025年から本格化する新ルールでは、相続が始まる前7年以内に行われた贈与が、相続財産に加算されることになりました。これは、より早い段階からの計画的な準備が重要になったことを意味します。年間110万円までの贈与なら贈与税がかからない「暦年贈与」という仕組みは続きますが、この新しいルールを念頭に置き、早めに専門家と相談しながら計画を立てることが、ご家族にとってもご自身にとっても安心につながります。
理由2:ご自身の「確かな意思」を反映させるため
遺言書の作成や生前贈与の契約といった法的な手続きは、ご自身の判断能力がはっきりしているうちにしか行えません。もし、将来的に認知症などで判断能力が低下してしまうと、ご自身の望む形での資産承継が非常に難しくなってしまいます。「まだまだ元気」な今だからこそ、落ち着いてご自身の想いを整理し、法的に有効な形で残しておくことができるのです。これは、ご自身の尊厳を守ることにも繋がります。
理由3:ご家族への「最後の思いやり」を形にするため
もしものことがあった時、何も準備がなければ、残されたご家族は悲しみに暮れる間もなく、複雑な手続きや財産の分割協議に追われることになります。それは、精神的にも肉体的にも大きな負担です。事前に準備をしておくことは、ご家族が直面するであろう困難を減らし、心穏やかにあなたを偲ぶ時間を作ってあげるという、何にも代えがたい「最後の思いやり」なのです。一番大切なのは、財産の分け方だけでなく「なぜそう考えたのか」というあなたの想いを伝えることです。
まずはここから!円満承継への3ステップ・やることリスト
□ ステップ1:想いと資産の「見える化」
まずは、難しく考えずにエンディングノートなどを活用して、「誰に、何を、どのように伝えたいか」というご自身の想いを書き出してみましょう。同時に、預貯金、不動産、保険など、どんな資産がどこにあるかを一覧にしておくと、ご家族も安心ですし、今後の計画も立てやすくなります。
□ ステップ2:家族との「対話のきっかけ」づくり
いきなり「相続の話をしよう」と切り出すのは、少し勇気がいるかもしれません。「将来のために、大事な書類の場所を共有しておきたくて」「この間の同窓会で、友達が準備を始めたと聞いてね」など、自然な会話のきっかけを探してみましょう。大切なのは、あなたの想いを伝え、ご家族の考えにも耳を傾ける、温かい対話の時間を持つことです。
□ ステップ3:「頼れる味方」を探してみる
すべてを一人で抱える必要はありません。お住まいの自治体や金融機関が開催する無料相談会に参加してみるのも良いでしょう。まずは全体像を把握するためにファイナンシャル・プランナー(FP)に相談し、そこから必要に応じて税理士や弁護士などの専門家を紹介してもらうという方法もおすすめです。
専門家はどこにいる? - 頼れる相談窓口と選び方
「誰に相談したらいいの?」という疑問にお答えします。それぞれに得意分野がありますので、ご自身の状況に合わせて頼れる味方を見つけましょう。
- 弁護士:ご家族間での意見の対立が予想される場合や、法的に間違いのない遺言書を作成したい場合に頼りになります。
- 税理士:相続税がどのくらいかかるか心配な方、節税を考えた生前贈与の計画を立てたい方の専門家です。
- 司法書士:ご自宅など不動産の名義変更(相続登記)の専門家です。遺言書の作成支援も行っています。
- 信託銀行:遺言書の保管から執行までを任せられる「遺言信託」など、資産管理や承継に関する総合的なサービスを提供しています。
- ファイナンシャル・プランナー(FP):お金に関する幅広い知識を持ち、まず何から始めるべきか、誰に相談すべきかといった、全体の交通整理をしてくれる心強いパートナーです。
選ぶ際のポイントは、専門知識はもちろんですが、「この人になら安心して話せる」と思える相性も大切です。初回の相談料やサービス内容を事前に確認し、納得できる専門家を見つけてください。
まとめ:心豊かな未来を描くための第一歩
今回は、大切な資産と想いを円満に次世代へ繋ぐための準備についてお話ししました。最後に、大切なポイントを振り返ってみましょう。
- 「争族」を防ぐ鍵は、財産の額ではなく、早めの準備とご家族との心温まる対話です。
- 遺言や生前贈与は、財産だけでなく「感謝の想い」を伝えるための大切なメッセージです。
- 2025年からの新ルールを念頭に、計画的な準備を始めることが、より一層重要になります。
- 一人で悩まず、信頼できる専門家を味方につけ、安心してこれからの人生を楽しみましょう。
さあ、今日からできる小さな一歩を踏み出してみませんか?
例えば、この週末、ご家族と一緒に昔のアルバムを開いてみるのはいかがでしょう。思い出を語り合う温かい時間こそが、円満な資産承継への何よりの第一歩です。
皆様のこれからの人生が、より一層輝き、安心に満ちたものとなりますよう、心から応援しております。
免責事項
本記事で提供される情報は、記事作成時点のものです。税制、年金、法律などの制度は将来変更される可能性がありますので、必ず公式サイトや専門家にご確認ください。
また、本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品、法律、税務上のアドバイスを行うものではありません。個別の状況に応じた最終的な決定は、税理士、弁護士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家にご相談の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。









